相続の準備として「遺言書を作っておけば安心」と思っている方は多いかもしれません。しかし、実際の相続の現場では「遺言書はあるけれど、どう執行すればいいか分からない」「相続人同士で揉めてしまった」といったトラブルが後を絶ちません。
そこで注目されているのが、信託銀行などの専門機関が遺言の内容を確実に実行する「遺言信託」です。遺言信託は、相続人の代わりに遺言執行を行ってくれる制度であり、遺された家族の負担を大きく軽減することができます。
本記事では、「遺言信託とは何か?」という基礎から、メリット・デメリット、費用の相場、信託銀行の選び方、そして行政書士の視点から見た実務上のポイントまで、徹底的に解説します。
目次
遺言信託の基本|遺言と信託の違いをまず理解しよう
そもそも「信託」とは何か?民事信託との違い
「信託」とは、財産の管理や処分を第三者に託す制度です。民法で定められた契約形態の一種で、委託者(財産を持つ人)が、受託者(信頼できる人や法人)に対して財産の管理・処分を委ね、受益者(財産の恩恵を受ける人)が利益を受け取るという三者関係で成り立ちます。
民事信託(家族信託)は、生前に契約することにより財産の移転や管理を行うものであり、「生きている間」に使う制度です。対して、遺言信託は、死後に効力を発揮する仕組みで、遺言の内容を実現するために信託機関が動く点が特徴です。
「遺言信託」と「遺言代用信託」の違い
似た名称で混同されがちなのが「遺言代用信託」です。
- 遺言信託:遺言書を信託銀行などに預けておき、死亡後に遺言執行人としてその内容を実行してもらう制度。
- 遺言代用信託:生前から信託契約を締結し、自分の死後に資産を特定の人へ移す仕組み。
つまり、遺言信託は遺言書の執行を他人に任せる制度、遺言代用信託は信託契約で遺言と同様の効果を生前に確保する制度です。
自筆証書遺言・公正証書遺言との関係
遺言信託を利用する場合、遺言書の形式として多いのは「公正証書遺言」です。自筆証書遺言も可能ですが、形式不備や内容の曖昧さによって無効になったり、検認手続きが必要になったりするリスクがあります。
信託銀行では、法的に有効な遺言書を確実に作成できるよう、公証人との連携を含めて支援してくれるのが一般的です。
遺言信託のメリットとデメリット
主なメリット(専門家による執行・相続人の負担軽減・トラブル回避)
遺言信託を利用することで得られる代表的なメリットは以下の通りです。
- 確実な遺言執行が可能になる
信託銀行は専門家として遺言内容を法的に適切に執行します。形式不備によるトラブルや、相続人の誤解・感情的な対立を最小限に抑えられます。 - 相続人の手間や負担を大幅に削減
戸籍収集、遺産分割協議書の作成、金融機関への届出などの煩雑な手続きを一任できます。遠方に住む相続人がいる場合や、家族構成が複雑な場合にとくに有効です。 - 相続争いを未然に防ぐ
公平な第三者が関与することで、「長男が勝手に手続きを進めた」などの不信感を避け、相続人全員が納得しやすい形で手続きを進められます。
デメリット(費用が高い・柔軟性に欠ける・一部の遺産に限定されがち)
一方で、以下のようなデメリットや注意点も存在します。
- 費用が比較的高額
遺言信託の契約時・執行時には高額な手数料が発生します。信託銀行によって異なりますが、執行手数料が数十万円~数百万円になることもあります。 - 柔軟な対応が難しい
契約後の内容変更は一定の手続きを要し、場合によっては再契約が必要です。生前の状況変化(家族関係や資産内容の変動)への即応性は低い傾向にあります。 - 信託の対象にできない財産もある
たとえば、日常使っている現金、個人間の債権債務、保険金の指定など、対象外の財産もあるため、他の対策との併用が必要なこともあります。
民事信託や家族信託と比較したときの注意点
| 比較項目 | 遺言信託 | 民事信託(家族信託) |
|---|---|---|
| 開始時期 | 死後に効力発生 | 生前から効力発生 |
| 管理者 | 信託銀行等の専門機関 | 家族・知人など |
| 柔軟性 | 低め | 高め |
| 法的サポート | 強い | 弱い(自己責任が大きい) |
| 費用 | 高い | 比較的安価だが自己管理必要 |
目的に応じて、適切な仕組みを選ぶことが肝心です。
遺言信託の費用相場と信託銀行の比較
初期費用(契約書作成料、信託設定費など)
契約時には以下のような費用がかかります。
- 遺言信託契約料:5万円〜15万円程度
- 公正証書作成費:1万円〜3万円(財産内容により異なる)
- 書類の収集・管理料:1万円前後(銀行による)
信託銀行はこの契約を一度締結すれば、契約者が死亡するまで保管・管理を継続します。
遺言執行時の手数料(遺産総額の〇%)
最も高額となるのが、遺言執行時の手数料です。
- 相続財産の〇%(例:1〜2%が一般的)
- 最低報酬額:30万円〜100万円
- 財産額が多いほど料率は下がる階段式のケースもあり
信託銀行ごとに料金体系が異なるため、事前に必ず見積もりを取りましょう。
大手信託銀行のサービス比較(例:三井住友信託・三菱UFJ信託・みずほ信託など)
| 銀行名 | 初期費用 | 執行手数料 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行 | 約11万円〜 | 最低33万円〜 | 全国対応・遺言作成支援も強い |
| 三菱UFJ信託銀行 | 約5.5万円〜 | 最低55万円〜 | 大手で安心感あり |
| みずほ信託銀行 | 約11万円〜 | 遺産の2.2% | 不動産に強みあり |
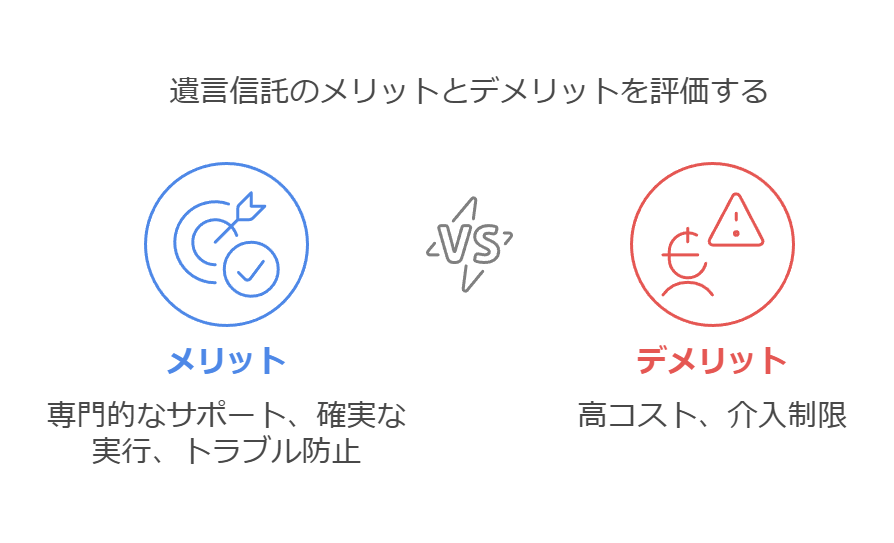
どんな人が遺言信託を使うべきか?
相続人同士のトラブルが懸念される人
- 子ども同士の仲が悪い
- 内縁の配偶者や認知した子がいる
- 再婚などで法定相続人が複雑化している
上記のようなケースでは、中立的な執行機関に任せることで争いを防止できます。
不動産や複雑な資産を持っている人
- アパート経営をしている
- 株式・外貨・信託商品などを所有している
- 海外資産を持っている
専門知識が必要な資産は、信託銀行などの専門家に任せるほうが安全です。
老後に認知症などのリスクを考える人
遺言信託と一緒に「家族信託」や「任意後見制度」と組み合わせることで、生前・死後の両方の財産管理対策を実現できます。
行政書士が教える|遺言信託を活用するための実務ポイント
信託銀行に任せるべき範囲と注意点
信託銀行に任せられるのは、基本的には「遺言の執行」と「財産の分配」に関する業務です。しかし、以下の点に注意が必要です。
- 法定相続人全員への通知・同意が必要な場面がある
→ 特定の遺産分割方法によっては、相続人全員の確認が求められることもあります。 - 遺言の内容が曖昧だと執行できないケースがある
→ 「〇〇に相応の金額を」といった記述は、銀行では判断できないため、明確な財産指定・分配方法が求められます。 - 信託銀行は遺言内容をそのまま執行するだけ
→ 相続人間の調整や説得は行ってくれないため、事前に遺言の意図を家族に共有しておくことが重要です。
民事信託・家族信託との併用は可能?
遺言信託と民事信託(家族信託)は、併用可能です。むしろ、以下のように使い分けるのが効果的です。
- 生前の財産管理・介護費用の捻出などには民事信託
- 死後の遺産分配や納税資金の確保には遺言信託
併用する際は、各信託で対象とする財産の重複や記述の矛盾がないよう、専門家(行政書士・弁護士・税理士)による設計が不可欠です。
自筆証書遺言と遺言信託の併用はどうなる?
遺言信託においても、遺言書の形式が重要です。
特に注意すべき点は以下の通りです。
- 自筆証書遺言を用いると、家庭裁判所での検認が必要
→ 執行までに時間がかかる - 信託銀行では公正証書遺言の作成を推奨している場合が多い
→ より迅速で確実な執行が可能
結論として、遺言信託を活用する際は、公正証書遺言の作成が望ましいといえるでしょう。
よくある質問(Q&A)
Q1. 遺言信託にしても遺留分は守られるの?
はい、遺留分は法律上保護されており、遺言信託でも無視はできません。
たとえば、全財産を特定の相続人1人に与えるという内容であっても、他の相続人には遺留分侵害額請求権が認められます。
したがって、遺言信託においても遺留分に配慮した設計が必要です。
Q2. 銀行が倒産したら信託財産はどうなる?
信託銀行が倒産しても、信託財産は分別管理されており、倒産の影響を受けにくい仕組みになっています。
これは「信託法」によって厳密に管理されているため、比較的安全性は高いと考えられます。
Q3. 子どもが未成年でも使える?
未成年の子どもを相続人に指定することは可能です。
ただし、財産の管理や名義変更などの手続きにおいては、法定代理人(親または後見人)の関与が必要になります。
Q4. 遺言信託はキャンセルできる?
生前であれば、遺言信託契約をいつでも解除することができます。
ただし、すでに支払った契約料や作成した書類の費用は返金されない場合があります。
また、遺言の内容の変更も可能ですが、その都度手数料や公正証書の再作成が必要です。
Q5. 行政書士や弁護士に依頼したほうが良い?
はい。信託銀行では基本的に法務相談は行っていないため、遺言内容の設計や法的な争点整理は行政書士や弁護士に相談することをおすすめします。
特に以下のようなケースでは、専門家の関与が有効です。
- 相続人間にトラブルの可能性がある
- 自社株や賃貸不動産など複雑な資産を持っている
- 相続税対策も含めた総合的な設計をしたい
まとめ|遺言信託で「安心」と「確実な相続」を実現するには
生前の準備が、遺された家族を救う
相続トラブルの多くは、「誰がどの財産をどのように引き継ぐのか」が明確でないことに起因します。遺言信託は、その「意思表示」と「執行」の両方を支える強力なツールです。
専門家と連携して最適な相続対策を選ぼう
遺言信託は便利な制度ですが、万能ではありません。民事信託や遺言代用信託、公正証書遺言といった他の制度との違いを理解し、専門家と連携することで最適な相続対策が実現します。
行政書士は、相続関係図の作成、財産目録の整理、遺言内容の設計など、実務面での重要な役割を担います。
信託銀行と行政書士のハイブリッド活用が、いま注目されています。




