不動産の相続で「共同名義」になった方へ
相続で受け継いだ不動産が、兄弟や親族との「共有名義」になっていませんか?
実はこれ、相続の中でもトラブルになりやすいパターンの一つです。
「親が亡くなって、とりあえず法定相続分で登記した」
「兄弟で話し合えば何とかなると思っていた」
そんな善意や常識的な判断が、後々の大きな揉め事の原因になることも少なくありません。
たとえば、
- 売却したいけど、他の共有者が同意しない
- リフォームの話が進まない
- 税金の負担が不公平
- 将来的に二次相続が発生し、関係者が倍増…
放っておくと、不動産は「共有の空き家」として資産価値を失うリスクもあります。
本記事でわかること
この記事では、以下のポイントを行政書士の視点からわかりやすく解説します。
✅ 「共同名義の相続」がなぜ問題なのか
✅ 相続後に共有名義になる仕組みと手続きの流れ
✅ 共有名義で起こりやすいトラブルと解決策
✅ 行政書士にできるサポート内容
✅ 公正証書遺言など揉めないための予防策
この記事を読むことで、「共有名義の相続って、実はまずいかも…」と気づいたあなたが、
早めに手を打つための第一歩を踏み出せるようになります。
まずは、よくある「共同名義相続」の仕組みから見ていきましょう。

目次
そもそも「共同名義の相続」とは?
相続発生後、共有名義になる仕組み
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産は、法定相続人に法定相続分に応じて承継されます。
このとき、不動産のように分けることが難しい財産は、一時的に共有状態になるのが一般的です。
たとえば、親が住んでいた家を相続する場合、兄弟が3人いれば、それぞれが1/3ずつの持分で「共有名義の所有者」となります。
この状態では、1人では勝手に売ることも、リフォームすることもできません。
法的には、相続が発生した時点で「相続人全員の共有財産」となるため、
その後の処理をきちんと進めないと、将来的に複雑な問題を引き起こすことになります。
法定相続分と登記の関係
不動産を相続した場合、相続登記(名義変更)を行う必要があります。
その際、誰がどのくらいの持分を持つかを明確にし、登記簿に記載します。
仮に、法定相続分通りに分けた場合は、
- 長男:3分の1
- 次男:3分の1
- 長女:3分の1
というように登記され、「共同名義」の不動産となります。
ここで注意したいのは、名義を共有にしたまま放置してしまうケースが非常に多いこと。
本来であれば、「誰が不動産を取得し、他の相続人にどのように分けるか」を遺産分割協議で決め、
そのうえで単独名義にするのが理想です。
なぜ共同名義が問題になるのか?

一見、「みんなで平等に持っていれば安心」と思えるかもしれませんが、
共有名義には以下のようなリスクが伴います。
- 共有者全員の同意がなければ、売却・賃貸などができない
- 1人が反対するだけで、手続きが進まない
- 固定資産税の支払いが不公平になりやすい
- 共有者の1人が死亡すると、さらに相続人が増えて複雑に
- 誰がどこに住むかでトラブルに発展しやすい
つまり、共有名義のままでは「身動きが取れない財産」になってしまう可能性が高いのです。
特に不動産の場合は「分割」できないため、共有状態が長引くと「空き家問題」や「相続人間の対立」につながることも少なくありません。
「とりあえず共有にしておこう」という判断が、後から大きな負担になって返ってくる。
それが、「共同名義相続」が持つ最大の落とし穴なのです。
共同名義にすると、こんなトラブルが起こる
不動産の売却・賃貸ができない
不動産を売却したい場合、共有者全員の合意が必要です。
たとえ1人でも「売りたくない」と言えば、売却はできません。
実際に多いケースが、「住んでいない兄弟が売却に同意せず、空き家のまま数年経ってしまった」という例。
この間にも固定資産税は発生し、維持管理のコストがのしかかります。
また、第三者に賃貸する場合も同様で、共有者の合意がないと契約できず、収益化ができないまま放置されるリスクもあります。
リフォームや修繕の合意がとれない
不動産は時間が経てば老朽化します。
屋根の補修、給排水設備の更新など、必要なメンテナンスが出てきますが…
これもまた、共有者全員の同意がないと実行できません。
「Aさんは住んでいるから直したい。でもBさんとCさんはお金を出したくない」
そんな状況が生まれると、実際に住んでいる人の生活に支障が出ることも。
しかも、修繕費を出す・出さないで兄弟関係にヒビが入ることも多く、
「相続が家族の関係を壊す」最たる原因の一つになりかねません。
固定資産税の支払い・名義変更で揉める
共有名義の不動産にかかる固定資産税は、登記上の代表者(納税義務者)に納付書が届くことが一般的です。
- 誰がいくら払うのか
- 誰が納税管理者になるのか
- 滞納があった場合、どう責任を分担するのか
こうした問題を事前に決めておかないと、「自分ばかりが払っている」という不満につながりやすくなります。
また、いざ名義変更(持分の整理)をしようと思っても、協力してもらえない共有者がいると話が進みません。
相続登記の義務化(2024年4月施行)もあり、早期の対応が求められるようになっています。
相続人の一人が亡くなった場合の二次相続のリスク
これが最も深刻なリスクかもしれません。
たとえば、兄弟3人で1/3ずつの共有名義だったとします。
そのうちの1人が亡くなり、その持分がさらに複数の相続人(配偶者や子)に分かれるとどうなるか?
- 登記上の所有者が3人 → 4人、5人…と増える
- 誰に話を通せばいいのかわからなくなる
- 1人でも反対すれば、話し合いが進まない
こうして、「共有状態が解消できないまま代を重ねる」という最悪の状態に陥るケースも。
結果として、不動産は売れない・貸せない・住めないという「負動産」と化し、管理責任だけが残ります
こんなはずじゃなかった…を防ぐには?
「うちは仲がいいから大丈夫」
「とりあえず法定相続分で登記しておけば安心」
そんなよかれと思った判断が、数年後に思わぬトラブルを招くことがあります。
だからこそ、「共有名義で放置すること」のリスクを知り、早めに行動を起こすことが大切です。
次の章では、実際にどのような手続きが必要なのか、その流れを解説します。
トラブルを防ぐには?相続手続きの基本の流れ
共有名義の相続トラブルを避けるためには、できるだけ早い段階で、明確な手続きを進めていくことが重要です。
この章では、相続後に不動産の名義や権利関係を整理するための基本的な流れを解説します。
ステップ①:遺産分割協議の重要性
不動産を含む財産は、法定相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合う必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議」と呼び、相続手続きの中核を担うプロセスです。
ポイントは以下の3点
- 法定相続人全員の参加が必要(1人でも欠けると無効)
- 話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめる
- 不動産の名義変更(相続登記)には、この協議書が必要になる
※話し合いがスムーズにいかない場合、専門家が間に入ることで感情的な対立を避けながら調整が可能です。
ステップ②:遺産分割協議書の作成と登記手続き
遺産分割協議で合意が取れたら、その内容を「遺産分割協議書」として文書化します。
行政書士は、この協議書の作成や署名押印のサポートも行っています。
協議書には、以下のような内容を明記します。
- 各相続人の氏名・住所・続柄
- 相続財産の内容(不動産・預金など)
- 誰がどの財産を取得するかの分配内容
協議書が完成したら、それを元に法務局で相続登記(名義変更)を行います。
これにより、不動産の「共有名義」から「単独名義」などに変更することが可能になります。
ステップ③:協議がまとまらない場合の対応(調停・審判)
「話し合いがどうしてもまとまらない…」
「特定の相続人が連絡を取ってくれない…」
そんなときは、家庭裁判所で「遺産分割調停」または「審判」という法的手段を取ることになります。
- 調停:家庭裁判所の調停委員を交えて話し合う手続き
- 審判:調停が成立しない場合、裁判官が強制的に分割内容を決める手続き
これらは時間も費用もかかる上、人間関係へのダメージも大きいため、
なるべく話し合いの段階でまとめることが望ましいです。
ステップ④:放置はNG!手続きを進めないリスクとは?
「とりあえず登記しないままでも問題ない」と思っている方も多いですが、それは非常に危険です。
- 相続登記が義務化(2024年4月~)され、怠ると10万円以下の過料も
- 共有状態が長期化すると、さらに相続が発生して権利関係が複雑に
- 不動産の売却・処分・活用の自由度が極端に下がる
手続きの放置は、時間が経つほど解決が難しくなるため、できるだけ早く整理しておくことが最善策です
専門家がいることで、手続きはもっとスムーズに
遺産分割協議や登記は、専門用語や法律文書が多く、慣れていない人にはハードルが高いものです。
行政書士に相談すれば、手続きの全体像を整理し、必要書類の作成や他士業との連携も含めてワンストップで対応可能です。
行政書士に相談するメリット
「相続で共有名義になってしまったけど、何から手を付ければいいかわからない」
そんなとき、行政書士に相談することが、スムーズで円満な解決への第一歩になります。
ここでは、行政書士に依頼する具体的なメリットを、わかりやすく解説していきます。

法的に有効な書類を作成できる
相続においては、形式不備や内容の不明確な書類が後のトラブルを招くケースが多く見られます。
行政書士は、以下のような法的に有効な文書を正確に作成できます。
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図(戸籍に基づく家系図)
- 各種申述書や委任状
- 公正証書遺言の作成サポート(文案作成・公証人とのやり取り)
正確な書類があれば、相続登記や金融機関での手続きもスムーズに進みます。
相続人間のコミュニケーションの橋渡しができる
兄弟間や親族間の話し合いは、どうしても感情的になりやすいものです。
「冷静に話し合おう」と思っても、ちょっとした誤解や言葉の行き違いで、関係がこじれてしまうことも。
行政書士は第三者として中立の立場で関わることができるため、
当事者同士では話しにくい内容も、円滑に伝えるサポートができます。
- 「こう伝えた方が相手に響く」
- 「法的にはこの主張が妥当です」
など、実務と人間関係の両面から支援できるのが、行政書士ならではの強みです。
税理士・司法書士との連携でワンストップ対応
相続に関する手続きは、行政書士だけで完結するものではありません。
不動産の名義変更登記は司法書士の業務、
相続税の申告や納税は税理士の分野です。
その点、当事務所では——
✅ 税理士・司法書士と連携し、チーム体制で相続手続きをサポート
✅ 窓口を一本化することで、お客様の手間を最小限に
✅ 専門家同士が情報を共有しながら、スピーディーな対応が可能
「何を、誰に、いつ相談すればいいのか…」という迷いをなくし、一括で安心できる体制を整えています。
費用感と相談のタイミング
「相談したいけど、いくらかかるか不安で…」という方も多いと思います。
当事務所では、初回相談は無料で承っております。
さらに…
- 料金は事前に明示・見積もり提示で安心
- 手続き内容ごとに明確な料金体系
- 他士業への依頼が必要な場合も、一括でご案内・調整可能
相続手続きにベストなタイミングは、「相続が発生してすぐ」です。
特に不動産が絡む場合は、時間が経つほど関係者が増えて話が複雑になるため、早めの行動が重要です。
こんな方におすすめです!
- 相続が発生し、不動産が兄弟で共有状態になっている
- 名義変更や遺産分割協議の方法がわからない
- 相続人との話し合いに不安がある
- 何をどこから手を付ければいいか、整理がつかない
- 公正証書遺言を作って「揉めない相続」にしたい
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
トラブルを未然に防ぐ「公正証書遺言」という選択肢
共有名義による相続トラブルは、発生してからでは手遅れになるケースも多いです。
そこで注目されているのが、「遺言書による事前の対策」です。
なかでも、法的効力が高く、実務上もっとも安心できる形式が「公正証書遺言」です。
なぜ遺言が必要なのか?
遺言書がない場合、相続は法定相続分に基づいて分けることになります。
その結果、不動産が共有名義になってしまい、売却や利用で揉めることが多々あります。
また、特定の相続人に不動産を相続させたい場合や、家族構成が複雑な場合などは、
明確な遺言書がないと「争族」になってしまうリスクが非常に高まります。
遺言書があれば、
- 誰に何を相続させるかを明確に指定できる
- 遺産分割協議が不要になるケースもある
- 家族間のトラブルを未然に防ぐことができる
「私がいなくなった後、家族が揉めないようにしたい」
その想いをカタチにする手段が、遺言書なのです。
自筆証書遺言との違いとメリット
遺言書には主に以下の2種類があります。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 手書きで自分で作成 | 費用がかからない | 形式不備・紛失・改ざんのリスク/家庭裁判所の検認が必要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人と作成 | 法的効力が高く、安全に保管される | 費用がかかる/作成にやや時間が必要 |
特に相続財産に不動産が含まれる場合や、特定の人に多く遺す事情がある場合は、
公正証書遺言のほうが圧倒的に安心です。
行政書士がサポートできること
公正証書遺言の作成には、以下のような準備が必要です。
- 相続関係図の作成(戸籍の収集)
- 財産目録の作成(不動産の登記情報・預金・有価証券など)
- 遺言内容の法的チェック
- 公証役場との事前打ち合わせ・日程調整
行政書士に依頼すれば、これらの手続きを一括で代行・サポートすることが可能です。
さらに、当事務所では税理士・司法書士との連携により、
節税対策や不動産登記のアドバイスまで含めた包括的な相続サポートをご提供しています。
公正証書遺言は「今すぐに」ではなく「今のうちに」
「まだ元気だから」「うちは揉めないから」
そう思って準備を後回しにしてしまう方が多いですが、
遺言書は自分で判断できるうちにしか作成できません。
相続は、いつ・誰に起こるかわかりません。
だからこそ、「今のうちに」準備しておくことが、ご家族への最大の思いやりになります。
よくあるご質問(Q&A)
相続や共有名義に関しては、「誰に聞けばいいかわからないけど、ちょっと気になる…」という声が多くあります。
ここでは、実際に当事務所へ寄せられるよくあるご質問をQ&A形式でご紹介します。
【Q1】共有名義のままでも、その家に住み続けることはできますか?
はい、共有者の1人がそのまま住むことは可能です。
ただし、共有者全員の合意があることが前提です。
後々、「勝手に住んでいる」「家賃を払ってほしい」などとトラブルになることもあるため、
事前に話し合いのうえで合意内容を文書にしておくことをおすすめします。
【Q2】共有名義の不動産を売却したい場合、どうすればいいですか?
基本的に、共有者全員の同意がなければ売却はできません。
そのため、まずは遺産分割協議で「誰が不動産を相続するか」を話し合い、単独名義に変更した上で売却するのが一般的です。
共有状態のままでは、買い手が見つからない・価格が下がるといった不利益があるため、
早めに名義整理を進めることが重要です。
【Q3】他の相続人が話し合いに応じてくれません。どうしたらいいですか?
その場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申し立てが検討されます。
調停では、裁判所が間に入って相続人同士の話し合いをサポートしてくれます。
ただし、調停・審判に発展すると時間も費用もかかる上、関係性がさらに悪化するリスクも。
できるだけ早い段階で、行政書士などの専門家が仲介し、円満な話し合いを目指すのが理想です。
【Q4】自分の持分だけを売ることはできますか?
法的には可能ですが、現実的には非常に難しいのが実情です。
持分のみの売却では、市場価値が大きく下がるため、買い手が見つからないことも多く、
さらに他の共有者との関係悪化にもつながりやすいです。
どうしても売却したい場合は、他の共有者に買い取ってもらう「持分買取」の交渉が一般的です。
【Q5】相続登記はすぐにしないといけませんか?
はい、2024年4月から相続登記は義務化されました。
これにより、不動産を相続した人は3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料の対象となります。
また、登記が未了のままだと、不動産の処分や名義変更ができず、将来的にトラブルの原因になります。
早めに登記を済ませておくことが、財産を守る第一歩です。
【Q6】まだ相続は発生していませんが、事前にできることはありますか?
はい、事前の準備こそが争族を防ぐカギです。
以下のような対策が可能です:
- 公正証書遺言の作成(誰に何を遺すかを明確に)
- 家族信託(認知症リスクを見越した財産管理)
- 不動産の名義整理や評価額の把握
元気なうちに準備しておくことで、残された家族の負担を大きく減らすことができます。
【Q7】行政書士と司法書士の違いって何ですか?
簡単に言うと、以下のような違いがあります:
| 項目 | 行政書士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 業務内容 | 書類作成、手続きの相談・代行 | 不動産登記、商業登記の代理 |
| 相続での役割 | 遺産分割協議書の作成、相続手続き全般のサポート | 不動産の名義変更(登記)の代理申請 |
| 他士業との連携 | 税理士・司法書士などと連携し、総合的に対応 | 単独での対応も多いが、行政書士と組むことも |
当事務所では、必要に応じて司法書士・税理士とチームで対応しますので、
「誰に頼めばいいかわからない」という方もご安心ください。
まとめ:共有名義の相続は専門家に早めの相談を
相続によって不動産が「共有名義」になるケースは非常に多く、
一見公平で無難な選択に見えますが、実は思わぬトラブルの温床になる可能性をはらんでいます。
共有名義のまま放置するリスクをおさらい
- 売却・賃貸・修繕に全員の同意が必要
- 固定資産税などの費用負担が不公平になりやすい
- 相続人の1人が亡くなると、さらに関係者が増えて複雑化
- 登記の放置により、法律上の過料(罰則)対象にもなる
「今は大丈夫だから…」と先延ばしにしてしまうことで、
後になって「もうどうにもならない」状況に陥ってしまうケースが少なくありません。
専門家のサポートで、スムーズかつ円満な相続を
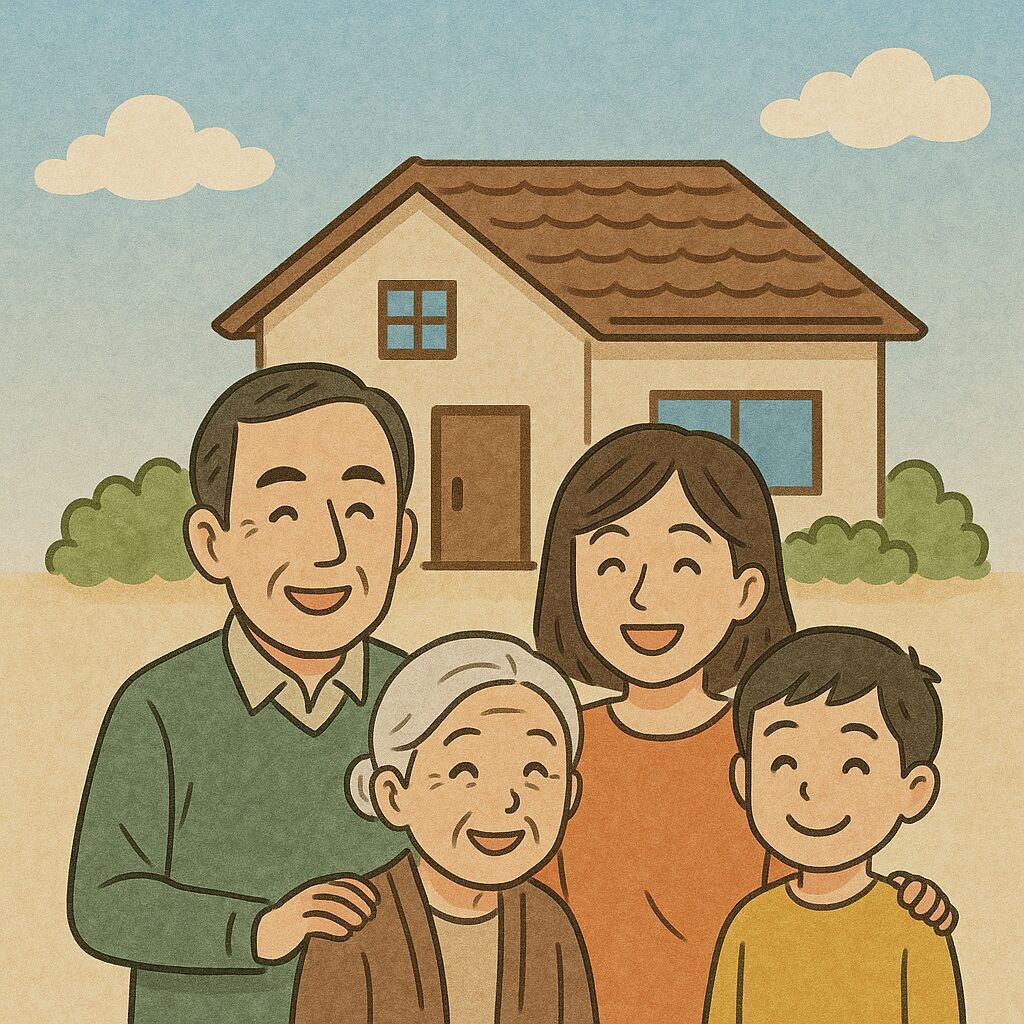
行政書士は、相続に関する書類作成や手続きのサポートを通じて、
ご家族の財産と関係を守るお手伝いができます。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図・財産目録の作成
- 公正証書遺言の準備
- 司法書士・税理士との連携による総合対応
「どう動けばいいか分からない」
「家族との関係が悪くなりそうで不安」
「自分1人でやるのは限界がある」
そんなときこそ、私たち専門家を頼ってください。
まずは無料相談から、お気軽にご連絡ください
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。
ご相談方法は以下の3つからお選びいただけます。
- 📞 お電話でのご相談:03-6820-3968
- 💬 お問い合わせフォームからのお問い合わせ(24時間受付)
- 🧑💻 オンライン面談(Zoom対応可)
「こんなこと聞いていいのかな?」という段階でも構いません。
一歩踏み出すことで、相続の悩みがスッと軽くなるはずです。
ぜひ、お気軽にご相談ください。




