親が亡くなったとき、残された家族が直面する大きな問題のひとつが「借金」です。
住宅ローンやカードローン、消費者金融からの借入など、亡くなったあとに督促状や請求が届いて初めて知るケースも少なくありません。親の借金は「自分が支払わなければならないの?」と不安に思う方も多いでしょう。¥実際、相続ではプラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金)も引き継がれる仕組みになっています。
ですが安心してください。法律上は「相続放棄」や「限定承認」といった選択肢があり、必ずしも借金を背負う必要はありません。
本記事では、親が借金を残して死んだ場合にどうなるのか、相続の流れと具体的な対処法、そして実際の体験談を交えて、わかりやすく解説します。

目次
親が亡くなったとき、借金はどうなる?
借金も相続の対象になる
相続というと「遺産=財産=プラスのもの」というイメージを持つ方が多いですが、実際にはマイナスの財産も含まれます。
つまり、親が生前に抱えていた借金や未払いのローン、連帯保証人としての責任なども相続財産の一部です。親が亡くなったからといって借金が消えることはなく、法定相続人に引き継がれるのが原則となります。
プラスの財産とマイナスの財産の関係
相続では「プラスの財産」と「マイナスの財産」がひとまとめに扱われます。

たとえば、親が自宅と預貯金を残していた一方で借金も抱えていた場合、その両方を引き継ぐのが基本です。
仮にプラスが500万円、マイナスが700万円なら、差し引きで200万円の赤字を背負ってしまうことになります。この「両方まとめて」というルールを理解しておかないと、知らないうちに借金を引き継ぐリスクがあるのです。
法定相続人に引き継がれる仕組み
親の借金は、相続人全員に法律で定められた割合で分配されます。
たとえば、父が亡くなり母と子ども二人が相続人だった場合、借金も母が2分の1、子どもたちがそれぞれ4分の1ずつ負担するのが原則です。「自分は関わりたくないから」と勝手に無視しても、債権者は法定相続人全員に請求できるため、避けられません。
借金を相続したくない場合は、後ほど説明する「相続放棄」や「限定承認」といった制度をきちんと利用する必要があります。
親の借金を確認する方法
親が亡くなったあと、「本当に借金があるのか?」「いくら残っているのか?」を確認することが、最初の大切なステップです。
借金の有無を早めに把握できれば、相続放棄や限定承認といった選択肢もスムーズに検討できます。ここでは、借金の確認方法を具体的に見ていきましょう。

通帳や契約書をチェックする
まずは自宅にある書類を確認します。ローン契約書、クレジットカードの明細、消費者金融の契約関係書類などが残されている場合、それが借金の手がかりになります。
通帳の記録にも注目です。毎月一定額が引き落とされている場合、ローン返済の可能性があります。
信用情報機関での照会
金融機関の契約が見つからないときは、信用情報機関で調べることができます。代表的なのは以下の3つです。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- JICC(日本信用情報機構)
- 全国銀行個人信用情報センター
相続人であれば、亡くなった人の信用情報を開示請求できる仕組みがあり、借入状況を客観的に確認できます。
郵便物や督促状から確認する
死亡後しばらくすると、債権者からの通知や督促状が届くこともあります。これが借金発覚のきっかけになるケースは非常に多いです。特に、消費者金融やカード会社からの封書には注意してチェックしましょう。
意外と多い「死後に発覚する借金」
親が借金を抱えていることを、家族に隠しているケースは珍しくありません。
「亡くなってから督促状が届き、初めて知った」という相談は実際に多く寄せられています。こうした場合でも、相続放棄には3か月という期限がありますので、できるだけ早く状況を整理する必要があります。
【体験談】父が亡くなってから督促状で借金が発覚したケース
ある50代男性は、父の死後に消費者金融から督促状が届き、父に数百万円の借金があることを初めて知ったそうです。家族は大きなショックを受けましたが、早めに家庭裁判所に相続放棄を申立てることで、借金を背負わずに済みました。
「親がそんな借金をしていたなんて…」という驚きと不安の中でも、迅速な手続きが家族を守るカギとなった事例です。
【体験談】相続人同士で情報がバラバラで大混乱したケース
別の事例では、相続人である兄弟がそれぞれ違う情報を持っており、借金の全容を把握するのに数か月を要しました。その間に相続放棄の期限が迫り、専門家に相談してなんとか間に合ったそうです。
「誰かが知っているだろう」と思い込まず、相続人全員で情報を共有することが、トラブル防止には不可欠です。
相続人がとれる3つの選択肢
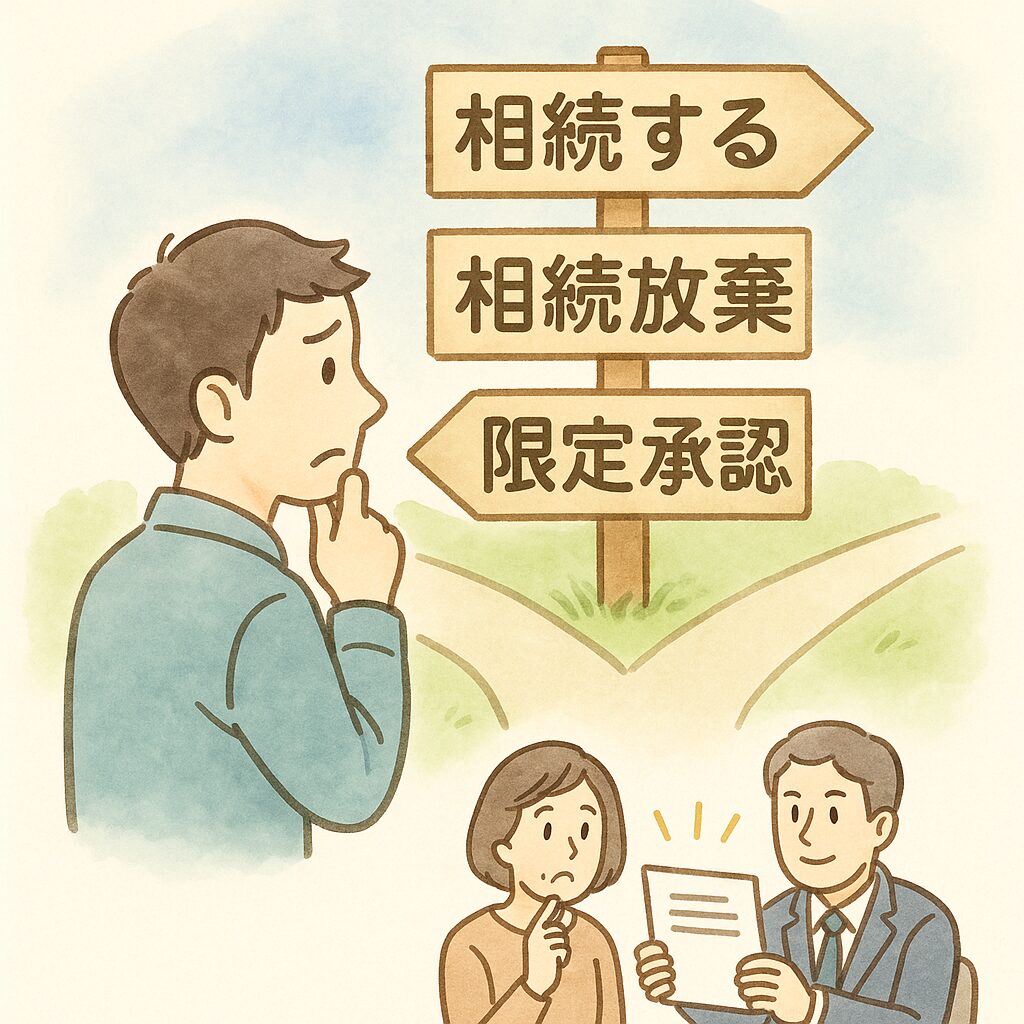
親の借金をどう扱うかは、相続人の判断次第です。借金をそのまま引き継ぐのか、それとも放棄するのか、法律では3つの選択肢が用意されています。それぞれの仕組みと注意点を整理しましょう。
単純承認(すべて相続する)
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。手続きが不要なので、何もしなければ自動的に単純承認した扱いになります。
注意点は、借金が多い場合でもそのまま背負ってしまう点です。相続財産を一部でも処分してしまった場合や、3か月の熟慮期間を過ぎてしまった場合には、自動的に単純承認とみなされます。
相続放棄(すべて拒否する)
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。親の借金を背負いたくない場合は、この手続きが最も確実です。
ただし、家庭裁判所に申立てを行う必要があり、期限は「相続開始を知った日から3か月以内」と決められています。また、一度放棄をすると撤回できません。
限定承認(プラスの範囲で借金を返す)
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する方法です。たとえば、親が300万円の預貯金と500万円の借金を残した場合、300万円の範囲内で借金を返し、それ以上は支払う必要がありません。
メリットは、財産がどのくらいあるかわからないときにも安心できる点です。ただし、相続人全員で手続きをする必要があるため、兄弟姉妹の合意が得られにくいのがデメリットです。
【体験談】相続放棄を選んで安心できた事例
ある40代女性は、父が残した借金を知り、不安で仕方なかったそうです。弁護士に相談して相続放棄を選択した結果、「自分の生活に影響しない」とわかり、大きな安心感を得られました。
「相続放棄」という仕組みを知らなければ、借金を背負っていたかもしれません。知識があるかどうかで、人生が大きく変わることもあるのです。
【体験談】限定承認を利用して、財産を守りつつ借金を整理できた
別の50代男性は、父が事業用の借金を残して亡くなったケースです。父の名義の不動産があったため相続放棄はしたくないと考え、兄弟と協力して限定承認を選びました。結果として、不動産を残しつつ借金も整理でき、「財産を守りながらリスクを避ける」というバランスのとれた対応ができたのです。けでは責任を免れないこともあります。
相続放棄を選ぶときの注意点
親の借金を背負いたくない場合、多くの人が選ぶのが「相続放棄」です。しかし、相続放棄にはいくつかの重要なルールと注意点があります。知らないまま進めてしまうと「放棄できなかった」という事態になりかねません。ここでは特に気をつけたいポイントを解説します。
家庭裁判所での手続きが必要
相続放棄は、書面で「やめます」と宣言するだけでは成立しません。必ず家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出し、正式に認められる必要があります。
提出先は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。手続きをしなければ、たとえ「相続しません」と口で言っても、法律的には相続した扱いになってしまいます。
申立期限は「相続開始を知ったときから3か月以内」

相続放棄の最大の注意点は、期限があることです。相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。もし期限を過ぎてしまうと、原則として自動的に単純承認(すべてを相続)したとみなされ、借金も背負うことになります。
放棄後の生活への影響(住んでいる家など)
相続放棄をすると、プラスの財産も一切受け取れなくなります。たとえば、親の持ち家に住んでいた場合、その不動産も相続できません。借金を避ける代わりに、生活環境が変わるリスクがあることを理解しておきましょう。
また、相続放棄をした人は最初から「相続人ではなかった」ことになります。そのため、次の順位の相続人(たとえば兄弟や甥姪)に借金の責任が移る場合もあります。家族全体で影響を考える必要があります。
【体験談】相続放棄の手続きをギリギリで間に合わせた話
ある男性は、父の死後に借金の存在を知ったものの、動揺して手続きを後回しにしてしまいました。気づいたときには、相続放棄の期限である3か月が目前に迫っていたのです。
慌てて専門家に相談し、必要書類を急いで準備した結果、期限ぎりぎりで相続放棄が受理されました。もしあと数日遅れていたら、数百万円の借金を背負うことになっていた可能性がありました。
この事例からもわかるように、相続放棄はスピードが命です。早めに行動することが、家族を守る大きなポイントになります。
もし借金が死後に発覚したらどうする?
親の借金は、生前から分かっていれば対処しやすいですが、実際には「亡くなってから督促状が届いて初めて知った」というケースがとても多いです。突然借金を知らされると、動揺してどうしていいかわからなくなりますよね。ここでは、死後に借金が発覚したときの対応方法を解説します。
3か月ルールを過ぎた場合の対応
相続放棄や限定承認は、原則として「相続開始を知ったときから3か月以内」に行わなければなりません。では、借金を知らずに3か月が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか。
実は「相続開始を知った日」=「亡くなった日」とは限りません。裁判所は、借金の存在を知った日を起点として判断してくれる場合があります。そのため、亡くなった直後には借金を知らなかったことを証明できれば、期限が過ぎても相続放棄が認められるケースもあります。
限定承認の活用方法
「プラスの財産も守りたいが、借金もある」という状況では、限定承認が役立ちます。たとえば、不動産や事業を相続したい場合に限定承認を使えば、プラスの財産を超える借金を負担せずに済みます。
ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があります。兄弟姉妹の中に反対する人がいると成立しません。そのため、事前の話し合いや専門家のサポートが不可欠です。
弁護士や行政書士に相談すべきケース
死後に借金が発覚すると、相続人同士で情報が錯綜して「どうすればいいのかわからない」と混乱することが多いです。借金の額が大きい場合や、相続人が複数いて意見が割れている場合は、専門家に早めに相談するのが得策です。
弁護士や行政書士に相談することで、相続放棄や限定承認の手続きがスムーズになり、期限切れのリスクも回避できます。
【体験談】3か月を過ぎてしまい、専門家に助けられたケース
ある40代男性は、母の死後に借金の存在を知らず、気づいたときにはすでに3か月が経過していました。「もうダメだ」と思いましたが、弁護士に相談したところ「借金を知った日」を起点にできると説明を受け、相続放棄が認められました。
「期限を過ぎても諦めないでよかった」との言葉が印象的です。専門家の知識と経験がなければ、借金を背負っていた可能性が高いでしょう。
【Q&A】知らなかった借金も相続しなきゃいけないの?
答えは「必ずしもそうではない」です。借金の存在を知らなかった場合、相続放棄が認められることがあります。重要なのは「借金を知った日」を基準にする点です。
ただし、すでにプラスの財産を処分してしまっていた場合などは、放棄できない可能性もあります。ケースごとに判断が分かれるため、迷ったら必ず専門家に確認しましょう。めていくことで、リスクを最小限に抑えることができます。迷ったら専門家である弁護士や行政書士に相談することも忘れないでください。
【実際の体験談】親の借金相続でこんなケースがありました
ここからは、実際に「親の借金相続」に直面した人たちの体験談をご紹介します。具体的な事例を知ることで、自分が同じ状況になったときにどう行動すればいいのか、よりイメージしやすくなるはずです。
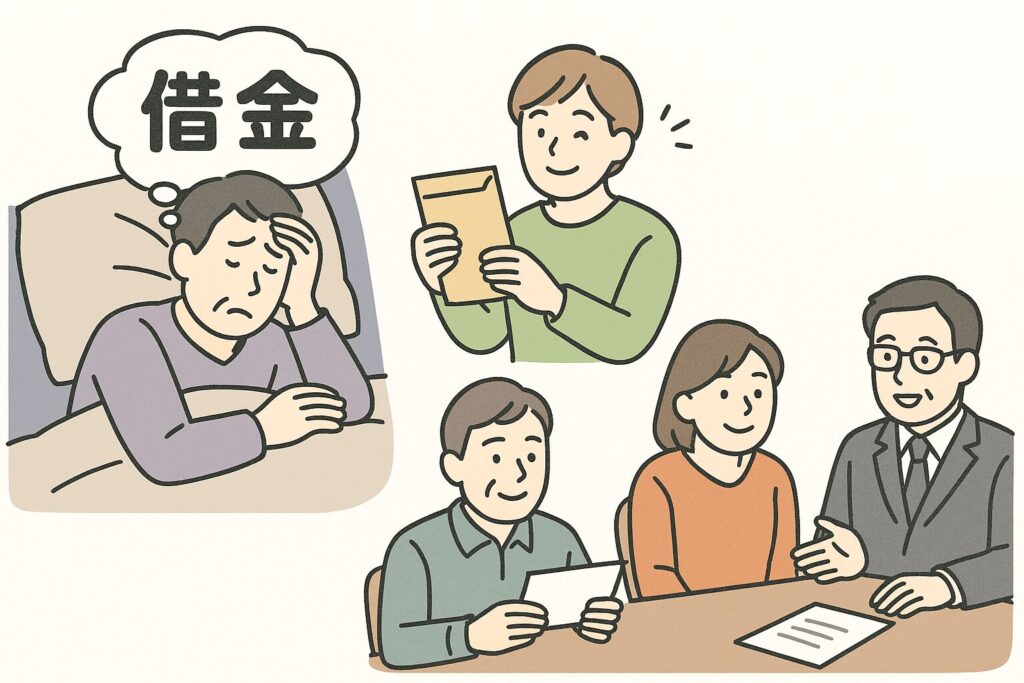
父の死後に督促状で借金が発覚したケース
50代男性のAさんは、父の死後しばらくして消費者金融から督促状が届き、初めて数百万円の借金があることを知りました。
家族は大きな衝撃を受けましたが、すぐに家庭裁判所に相続放棄を申立てたことで、借金を背負わずに済んだそうです。
「亡くなってから知ることもある」と理解していたからこそ、落ち着いて動けた事例です。
相続放棄を選んで安心できた事例
40代女性のBさんは、父の借金が残されていると知り、大きな不安を抱きました。弁護士に相談した結果、相続放棄の手続きを行い、負債を引き継がずに済んだのです。
「もし知らないまま過ごしていたら、いつ請求が来るか怯えていたと思う」と語り、相続放棄を選んだことで心から安心できたそうです。
限定承認で財産を守りつつ借金を整理した事例
事業を営んでいた父が亡くなり、多額の借金と不動産を残したCさん兄弟。相続放棄をすると不動産まで失うことになるため、話し合いの末に「限定承認」を選びました。
結果として、父の不動産を守りつつ、借金はプラスの財産の範囲内で整理できました。
「家族で意見が一致したからこそ実現できた」と振り返っています。
相続放棄の手続きをギリギリで間に合わせた話
Dさんは、親の借金を知っていたものの、慌ただしさに追われて手続きを先延ばしにしていました。気づけば、相続放棄の期限である3か月が目前に…。
専門家のサポートを受けながら急いで申立てを行い、なんとか期限内に受理されました。
「あと数日遅れていたら、多額の借金を背負っていた」と冷や汗をかいたそうです。
3か月を過ぎてしまい、専門家に助けられたケース
母の借金を知らずに3か月以上経過してしまったEさん。当初は「もう諦めるしかない」と思いましたが、弁護士に相談したところ「借金を知った日」からのカウントが可能だと判明しました。
その結果、相続放棄が認められ、借金を免れることができました。専門家に頼ることで救われることも多いのです。
専門家に早めに相談してトラブルを回避できた例
Fさんは、父の借金があると聞いてすぐに行政書士に相談しました。そのおかげで、必要な書類を早めに揃え、スムーズに相続放棄を完了。兄弟間でのトラブルも起きませんでした。
「自分たちだけで判断していたら、もめていたかもしれない。専門家の存在は大きい」と実感した体験談です。
よくある質問(Q&A)
親の借金に関する相続問題は、多くの人にとって初めての経験です。そのため、基本的なことから誤解されやすいことまで、さまざまな疑問が生まれます。ここでは、特によく寄せられる質問にQ&A形式で答えていきます。
Q1:親の借金を子どもが必ず払わなければならないの?
A:いいえ。必ずしもそうではありません。
親の借金は相続財産の一部として相続人に引き継がれますが、相続放棄をすれば子どもが支払う必要はありません。相続放棄を行えば「最初から相続人ではなかった」扱いになるため、債権者から請求されることはありません。
Q2:相続放棄すると親の遺産は一切受け取れないの?
A:はい、その通りです。
相続放棄をすると、プラスの財産も含めて一切相続できなくなります。たとえば、預貯金や不動産などがあっても受け取れません。借金を背負いたくない場合には有効ですが、「資産も同時に失う」という点には注意が必要です。
Q3:兄弟の一人だけが相続放棄できる?
A:可能です。
相続放棄は相続人ごとに判断できるため、兄弟のうち一人だけが放棄し、他の兄弟は相続するという形も取れます。ただし、その場合は放棄した人の取り分が他の相続人に回ることになります。結果的に、残った相続人が借金を負担する割合が増える点に注意が必要です。
Q4:相続放棄後に借金の取り立てが来たらどうすればいい?
A:家庭裁判所で受理された「相続放棄申述受理証明書」を提示しましょう。
相続放棄が認められていれば、あなたに請求することはできません。証明書を債権者に提示すれば取り立ては止まります。もし相手が取り立てをやめない場合は、弁護士に相談することで速やかに解決できます。
相続トラブルを避けるために知っておきたいこと
親が借金を残して亡くなった場合、家族の間で「どう対応するか」をめぐって意見が分かれることがあります。財産や借金が絡む相続問題は、感情的になりやすく、トラブルに発展するケースも少なくありません。ここでは、相続トラブルを回避するために知っておきたいポイントをまとめます。
相続人同士での話し合いが大切
借金相続は、相続人全員に関わる問題です。誰か一人が勝手に判断すると「そんなの聞いていない」と不満が生まれ、争いにつながることがあります。
特に「相続放棄」や「限定承認」は、手続きに相続人全員の同意や理解が必要な場合があるため、必ず話し合いの場を設けましょう。家族間で情報を共有し、「借金をどう処理するのか」をオープンに話し合うことが、トラブル防止の第一歩です。
親が生前にできる準備(遺言・生前整理)
借金があるかもしれないと感じたら、親が元気なうちに準備してもらうのも有効です。
- 借金やローンの契約状況を整理しておく
- 借入先や残高をリスト化する
- 不動産や預貯金などのプラスの財産とあわせて「資産・負債の全体像」を把握する
これらを遺言やエンディングノートに残しておけば、家族が突然の借金に驚くリスクを減らせます。
専門家に相談するメリット
借金相続は法律知識が必要であり、素人判断では間違った方向に進んでしまうこともあります。弁護士や行政書士に相談するメリットは以下の通りです。
- 相続放棄や限定承認など、最適な手続きを選べる
- 期限切れなどのリスクを防げる
- 相続人同士の対立を第三者の立場から調整してもらえる
特に相続人が複数いる場合や、借金と財産の金額が大きい場合は、専門家のサポートが心強い味方になります。
【体験談】専門家に早めに相談してトラブルを回避できた
Fさんは、父が残した借金について相続人の兄弟と意見が割れそうになりました。そこで、弁護士に相談したところ、相続放棄をスムーズに進めるための具体的な手順を提示してもらえました。
結果的に、兄弟間の対立は起こらず、手続きも期限内に完了。Fさんは「専門家が間に入ってくれたおかげで家族の関係も守れた」と安心できたそうです。
まとめ|親が借金を残して死んだら、まず落ち着いて行動を
親が亡くなった後に借金が発覚すると、多くの人が動揺し「自分が払わなければならないのか」と不安に押しつぶされそうになります。しかし、法律上は対処法がきちんと用意されています。焦らず、順を追って行動することが大切です。
焦らず状況を確認する
まずは「本当に借金があるのか」「どのくらいの金額なのか」を冷静に調べましょう。通帳、契約書、郵便物、信用情報機関での照会など、確認できる手段はいくつもあります。曖昧なまま判断せず、事実を把握することが第一歩です。
相続放棄や限定承認でリスク回避できる
借金も相続の対象になりますが、相続放棄や限定承認を使えば必ずしも背負う必要はありません。
- 借金を一切引き継ぎたくないなら「相続放棄」
- プラスの財産を守りつつ借金も整理したいなら「限定承認」
自分や家族にとって最も適した方法を選ぶことが、安心への近道です。
迷ったら専門家に相談しよう

「期限に間に合うか不安」「相続人同士で意見が割れている」など、自分たちだけで解決が難しいと感じたら、迷わず専門家に相談してください。弁護士や行政書士は、手続きの進め方だけでなく、家族間の調整役としても心強い存在です。
最後に
親が借金を残して死んだとしても、冷静に動けば家族が借金を背負う必要はありません。
大切なのは、「早めに事実を確認する」「期限を意識する」「必要なら専門家に相談する」ことです。
不安を一人で抱え込まず、正しい知識と行動で家族の未来を守りましょう。




