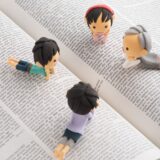目次
親の認知症と相続、「気づいたときには手遅れだった」実例も
「父の物忘れが気になるようになってきたけど、まだ元気だし大丈夫だろう」
そう思っていた矢先、医師から「軽度の認知症」との診断を受けたAさん。
「まさか、こんなに早く来るとは……」
そして一番驚いたのは、もう遺言書が作れないかもしれないという事実でした。
高齢化社会が進む日本では、「親の認知症」と「相続問題」が切っても切れない関係になりつつあります。
それにもかかわらず、多くのご家庭ではまだ“自分ごと”として備えていないのが現実です。
行政書士として、相続や認知症に関するご相談を受けていると、「もっと早く相談してくれていれば……」というケースによく出会います。中には、親が認知症を発症したことで、遺言が無効になったり、不動産の売却ができなくなったりと、深刻な事態に発展してしまったご家庭もありました。
この記事では、
- 認知症が相続にどのような影響を与えるのか
- 発症前にやっておくべきこと
- 発症後にできる対応策
について、行政書士の視点でわかりやすく、具体的に解説していきます。
あなたのご家族が将来困らないために、そして「やっておけばよかった」と後悔しないために。
今このタイミングで、相続と認知症対策について一緒に考えてみませんか?
セクション1:親が認知症になると、相続はどう変わるのか?【基本知識】
親が認知症になると、相続手続きはどう変わるのでしょうか?
結論から言うと、「本人の意思確認が必要な手続き」がほぼ不可能になります。
たとえば、以下のようなケースが発生します。
- 遺言書を新たに作る or 書き直すことができない
- 生前贈与の意思表示ができないため、節税対策が打てない
- 親名義の不動産を売却・名義変更することができない
- 親の預金を動かすことができない(凍結される場合も)
このように、認知症の進行とともに法律的な意思能力が失われると、財産の管理や処分、相続対策がまったくできなくなってしまうのです。
相続凍結とは?
相続凍結とは、親が認知症を発症したことによって、財産に関する手続きが一切できなくなる状態を指します。
- 不動産売却をしたいけど、親の同意が取れない
- 預金を引き出したいけど、金融機関が拒否
- 名義変更や契約更新に本人の署名が必要だけど、サインができない
このような状態になると、家族が代わりに対応したくても、「家族だからといって代筆・代行はできない」のが法律の大原則です。
行政書士として見てきた現場のリアル
行政書士として実際にご相談を受ける中で、「うちの親、最近ちょっと忘れっぽくなってきたから、そろそろ遺言でも……」と相談に来られる方は少なくありません。
ですが、医師の診断やご本人の状態によっては、もう遺言書作成ができないと判断されることもあります。
そうなると、相続トラブルや資産の凍結リスクに直面し、何年も動かせない財産を抱えることになります。
セクション2:遺言は本人の意思が必要。認知症では作成できない
「認知症になっても、話が通じるなら遺言ぐらい書けるのでは?」
そんなふうに思う方は少なくありません。
しかし、相続に関わる書類、特に遺言書の作成においては、非常に厳しい条件が求められます。
「判断能力」がないと、遺言は無効になる
遺言書は、被相続人(遺言を書く人)が亡くなった後に効力を持つ、本人の最後の意思表示です。
そのため法律上、「作成時点での判断能力(=意思能力)」が厳密に問われます。
判断能力がない状態で作成された遺言書は、たとえ形式が整っていたとしても無効とされてしまうのです。
医師の診断書があっても安心とは限らない
実際には、認知症と診断された方でも症状の進行には個人差があり、「まだ会話はできるし、意思表示もできている」と感じることも多いでしょう。
しかし、法律の世界では元気そうに見えるでは足りません。
- ある方が自筆証書遺言を作成
- しかし、当時すでに認知症の診断歴があり、日記などからも記憶の混乱が見られた
- 相続開始後、他の相続人が「意思能力がなかった」と主張し、遺言無効の訴訟へ
→ 最終的に、遺言が無効とされてしまった事例もあります
家族が気づきにくい「認知症の初期症状」
認知症は、ゆるやかに、そして目に見えない形で進行していきます。
そのため、「あのときはまだ大丈夫だったと思う」と後から思っても、法律的にはアウトだったということが少なくありません。
- 同じ話を何度も繰り返す
- 曜日や時間の感覚があいまいになる
- お金の管理ができなくなってきた
- 怒りっぽくなる、些細なことで混乱する
これらはよくある認知症の初期症状ですが、家族はつい「年のせいかな」と見逃してしまいがちです。
しかし、遺言の可否がたった数ヶ月の判断の遅れで決まってしまうこともあるのです。
公正証書遺言でも「判断能力の証明」が重要
公証役場で作る公正証書遺言は、作成時に公証人が立ち会い、形式的なミスがないようにチェックしてくれます。
しかし、それでも認知症の進行があると、公証人が「本人に意思能力がない」と判断して作成を断るケースもあります。
そのため、以下のような配慮が求められます。
- 必要に応じて、医師による「意思能力に関する診断書」を準備
- 家族や専門家が日程調整・内容整理をサポートし、本人の理解を深める
- 状況が微妙な場合は、行政書士など専門家が事前に状態を確認するのが安全
まとめ:遺言は「早ければ早いほどいい」
遺言書は、本人の想いを家族に正確に伝えるための大切な手段です。
ですが、認知症のリスクがある年齢になると、「今は元気だからまだ大丈夫」ではなく、「元気な今だからこそ作っておこう」という意識が何よりも大切です。
判断能力が失われてからでは、遺言は一切できません。
家族のためにも、ご自身の意思を守るためにも、早めの準備を強くおすすめします。
セクション3:何もしなかった家族が直面した、後悔の事例
「そのときは、まだ大丈夫だと思っていました」
認知症と相続のご相談で、最もよく聞く言葉の一つです。
しかし実際には、「あと半年早ければ…」「あのとき相談していれば…」という”たら・れば”の後悔が、多くの家族にのしかかっています。
ここでは、行政書士として実際に対応してきたケースから、「何もしなかったことで起こった現実」をご紹介します。
ケース①:遺言を作らずに親が認知症 → 遺産分割協議がまとまらない
80代の父親が突然、軽度認知症と診断されたAさん一家。
「遺言書はまだ作ってないけど、うちは仲がいいから揉めない」と安心していました。
ところが、相続が発生すると、兄弟姉妹間で意見が割れ、遺産分割協議が進まずに膠着。
しかも、父親の判断能力がすでに不十分と診断されていたため、本人が協議に参加できず、手続きが完全に止まってしまいました。
最終的には家庭裁判所に成年後見人を申し立てることになり、解決までに2年以上を要しました。
▶ このケースの教訓
認知症になると、相続協議が「当事者不在」となり、誰も動けなくなる。
公正証書遺言を事前に作っておけば、協議自体が不要になることも。
ケース②:生前贈与がストップ → 相続税対策が崩壊
Bさんは、生前に親の財産を整理しながら、贈与税の非課税枠を利用して毎年少しずつ贈与を行っていました。
しかし、親が軽度認知症と診断されてからは、「もう意思確認ができない」と判断され、贈与を継続できなくなりました。
結果として、残された財産が一括で相続対象となり、相続税の負担が予定より数百万円も増加。
「あと1年続けられていれば…」という後悔の声が聞かれました。
▶ このケースの教訓
生前贈与は「本人の意思確認」が必須
認知症になると、節税対策がすべて停止するリスクあり
ケース③:空き家の売却ができず、固定資産税が家計を圧迫
Cさんの父親は、郊外に不動産を所有していました。
一人暮らしが難しくなり施設に入所したタイミングで、「空き家になった自宅を売却したい」と家族が希望。
しかし、すでに軽度認知症の診断を受けていたため、父の名義での売却契約は結べず…。
成年後見制度を利用しようとしたものの、手続きや後見人の選定に時間がかかり、売却まで約1年半かかってしまいました。
その間、空き家の管理費用・修繕費・固定資産税が家計を圧迫。
「こんなに動かせないとは思わなかった」というのが率直な感想だったそうです。
▶ このケースの教訓
不動産売却にも「本人の判断能力」が必須
家族信託などの早期対策で、柔軟な資産管理が可能になる
まとめ:気づいたときが「一番早いタイミング」
ここで紹介したのは、すべて実際に起きたことです。
「うちは大丈夫」「まだ元気だから」と思っていたご家族ほど、準備を後回しにして後悔されています。
重要なのは、親が元気な今に何をしておくか。
相続は、亡くなってから始まるものではありません。
認知症になる前から、すでに始まっていると考えて行動することが、家族全体を守る最善策になります。
セクション4:早めにやっておくべき4つの準備とは?
認知症によって財産管理ができなくなる前に、どれだけ備えておけるかが家族を守るカギです。
ここでは、行政書士として多くのご相談を受けてきた中で、特に効果的だった「4つの事前準備」をご紹介します。
① 公正証書遺言の作成
最も優先順位が高いのが、遺言書の作成です。
特に、家庭で揉める要因があるケース(たとえば、相続人が複数・特定の人に財産を残したい・再婚家庭など)では必須といえます。
公正証書遺言がおすすめな理由
- 公証人が関与するため、形式ミスや偽造の心配がない
- 医師の診断書を添付することで、後から意思能力を争われにくい
- 原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざんのリスクもゼロ
ポイント
「いつか遺言を」と思っていても、判断力が少しでも落ちれば作成そのものができなくなるため、早めの行動が大切です。
② 任意後見契約の締結
認知症になる前に、将来的な判断能力の低下に備えて「自分の後見人」を自分で選んでおける制度が「任意後見契約」です。
これは、将来「判断力が低下したと医師に診断されたとき」に発動し、あらかじめ選んでおいた信頼できる家族や専門家が財産管理を行えるようになります。
任意後見のメリット
- 自分の希望する人を「後見人」として指定できる
- 自宅や預貯金の管理、不動産売却などを任せられる
- 公正証書で契約するため、法的に有効なしくみ
ポイント
契約には本人の意思確認が必要なため、「元気なうち」でないと利用できません。
「将来、家族に迷惑をかけたくない」と考える方には非常に有効な制度です。
③ 家族信託の活用
家族信託はここ数年で注目が高まっている制度で、「自分の財産を信頼できる家族に託し、運用・管理してもらう契約」です。
認知症によって判断能力がなくなっても、信託契約に基づいて、受託者(家族など)が財産を柔軟に動かすことが可能です。
家族信託の主な用途
- 不動産の売却・管理
- 預貯金の運用や生活費の支出
- 二次相続(たとえば「次は孫に渡したい」など)の指定
ポイント
家族信託は設計の自由度が高いため、遺言や成年後見では実現できない柔軟な財産管理が可能になります。
ただし、設計には専門知識が必要なので、行政書士などの専門家への相談が重要です。
④ 財産の棚卸と名義の整理
制度を活用する以前に、まずやるべきは「家族で財産の全体像を把握すること」です。
- 不動産の所在地と名義は誰か?
- 預貯金口座はいくつあり、どこにあるのか?
- 借入・保証など負債はあるか?
- 相続人は誰か?(戸籍チェックも含めて)
ポイント
把握していなければ、認知症発症後に何も手が打てなくなるだけでなく、家族間で「知らなかった」「言っていなかった」と揉める原因になります。
「うちは大した財産がないから大丈夫」という方ほど、実は名義が曖昧だったり、手続きでトラブルが起きやすい傾向があります。
まとめ:4つの対策は「できる順」で構いません
一気にすべて整える必要はありません。
大切なのは、「知った今、できることから1つずつ始めること」です。
- ✅ 遺言書の準備
- ✅ 任意後見の検討
- ✅ 家族信託を活用した柔軟な財産管理
- ✅ 財産の棚卸と名義チェック
これらを一つずつ整えていくだけで、将来の相続リスクを大幅に減らすことができます。
セクション5:それでも発症してしまった場合に使える制度
「備えが間に合わなかった」「もう親が認知症と診断されてしまった」
そんなときでも、すべてを諦める必要はありません。
たしかに、遺言や信託など本人の意思が必要な制度は使えなくなりますが、代わりに活用できる仕組みもあります。
ここでは、認知症発症後に利用できる2つの制度を解説します。
① 成年後見制度
成年後見制度とは、判断能力が低下した方の財産や契約関係を法律的に保護・代理する制度です。
家庭裁判所を通じて、本人に代わって財産管理などを行う「後見人」が選任されます。
法定後見制度のしくみ
すでに認知症を発症している場合は、「法定後見制度」を利用することになります。
- 家族や行政書士などが家庭裁判所に申し立て
- 医師の診断書を提出し、審理を経て後見人が選任される
- 後見人は、裁判所の監督のもとで本人の財産を管理・契約などを代行
たとえば
- 預貯金の管理・支払い
- 不動産の売却
- 施設入所の契約手続き
などを、家族の代わりに「法的に正しく」行うことができます。
ただし、制度の限界も知っておくことが大切
成年後見制度はあくまで「本人の保護」が目的のため、自由な運用や節税・贈与などは基本的にできません。
主な注意点
- 裁判所の監督下で手続きが厳格
- 定期的な報告義務や費用負担がある(年間数万円〜)
- 財産の処分には裁判所の許可が必要になるケースも
- 相続税対策や柔軟な資産運用はほとんど不可能
ポイント
あくまで「必要最低限の財産管理・契約の代理」として使う制度であることを理解しておく必要があります。
② 任意後見契約(すでに締結済みの場合)
前のセクションで紹介した任意後見契約を、元気なうちに結んでいた場合には、認知症発症後にそれを「発効」することができます。
発効の流れ
- 医師の診断書を取得し、家庭裁判所に監督人選任の申し立て
- 任意後見人+任意後見監督人の体制がスタート
- 以降、契約の範囲内で任意後見人が財産管理を行う
任意後見契約が発効していると、信頼できる人が事前の契約内容に沿って、柔軟に対応できるため、トラブルを大きく減らすことが可能です。
まとめ:発症後の制度には「できること」と「できないこと」がある
認知症を発症してしまった場合でも、
- 成年後見制度を利用することで、最低限の財産管理・契約手続きが可能
- 任意後見契約を事前に結んでいれば、スムーズな管理・対応ができる
ただし、どちらの制度も「節税・資産の移動・遺言」などには対応できない点に注意が必要です。
だからこそ、「発症後でもできる制度がある」という安心感と同時に、「発症前にしかできないことがたくさんある」という危機意識も忘れてはいけません。
セクション6:実際に行政書士として対応した、リアルな現場とアドバイス
認知症と相続の問題は、マニュアルどおりにいかないことばかりです。
制度や法律だけを知っていても、それだけでは対応しきれないのが現場の実情。
ここでは、行政書士として実際にご相談を受けたケースや、現場で感じた“本音のアドバイス”をお伝えします。
「もう少し早ければ…」と何度も感じた
あるご相談では、認知症の診断を受けたばかりのお父様について、
「今から遺言書って間に合いますか?」というご質問をいただきました。
状態を丁寧にヒアリングした上で、医師の診断書も確認。
その結果、公正証書遺言の作成を急ぎでサポートし、なんとか間に合ったケースもありました。
しかしその一方で、「数ヶ月前なら可能だったはず…」というご相談も少なくありません。
本人は意思があるように見えても、診断記録や日常の行動履歴から判断能力の不十分さが明らかになり、遺言書が法的に有効とならないリスクがあるのです。
🟢 現場で感じること:
「まだ元気なうちに、ちょっと専門家に相談しておこうかな」
——この一歩があるかないかで、将来の家族の負担が大きく変わります。
揉める家族、まとまる家族——違いは「準備」と「対話」
印象に残っているご家庭では、親御さんの判断能力が残っているうちに、
- 財産の一覧を整理
- 遺言書を作成
- 家族で話し合いの場を設ける
という段取りをしっかり整えていたことで、相続が発生した際も、全員が納得した状態でスムーズに進められました。
一方、何も準備していなかった別のケースでは、兄弟間で「お金の使い込み疑惑」や「介護の不公平感」などが浮上。
家庭裁判所を巻き込んで争いに発展し、精神的にも経済的にも大きな負担となってしまいました。
🟡 違いはたったひとつ。「前もって準備していたかどうか」だけです。
制度を“知っている”と“使える”は違う
成年後見や家族信託など、制度そのものはネットでも情報収集できます。
しかし、実際にそれを“どう自分たちの家庭に当てはめるか”は、ケースバイケースです。
たとえば:
- 持ち家は誰の名義か?売却の必要はあるか?
- 兄弟の関係性は?介護の分担状況は?
- 財産の種類と金額は?非課税枠を活用した方が良いか?
こうした細かい条件を整理してはじめて、
「信託が良いのか、任意後見が良いのか、それとも遺言で十分なのか」
という具体的な判断ができるようになります。
制度の知識よりも、実行するタイミングが未来を左右します。
プロからの本音アドバイス:迷ったら、まず一度話してみてください
- 認知症対策、何から始めていいか分からない
- 兄弟で話ができていないけど不安
- 相続って、誰に何を相談すればいいのかピンとこない
こうした気持ち、実はどのご家庭でもほとんど同じです。
だからこそ、「ちょっと気になる」くらいの段階で相談しておくことが最大の防御策になります。
行政書士は、相続や成年後見・信託といった制度に精通しつつ、家族間の調整や手続きの伴走役としてもお手伝いできます。
あなたのご家族が、これからも安心して暮らせるように。
ぜひ、専門家の力を上手に使ってください。
セクション7:よくある質問Q&A【認知症×相続のリアル】
ここでは、行政書士として実際によく受ける質問をQ&A形式でまとめました。
「うちもこれに当てはまるかも」と思ったら、早めに行動するためのきっかけにしてください。
Q1:認知症でも、ちゃんと話せれば遺言は書けますよね?
A:いいえ、「話せる=遺言できる」ではありません。
遺言書の作成には、「作成時点での判断能力」が法的に必要です。
たとえ普通に会話ができても、内容の理解や意思表示に曖昧な点があれば、後に遺言が無効と判断される可能性があります。
特に公正証書遺言を作成する際、公証人が「判断能力に疑いがある」と感じた場合は、作成を断られることも。
「今なら大丈夫」は、専門家と一緒に判断するのが安心です。
Q2:成年後見って、どうやって申し込むんですか?
A:家庭裁判所に申し立てを行います。
法定後見制度を利用する場合は、家族や関係者が家庭裁判所に対して「後見開始の申し立て」を行う必要があります。
主な流れは以下の通りです。
- 申立書類の準備(診断書など含む)
- 家庭裁判所への提出
- 面談・審理
- 後見人の選任(家族とは限らない)
申し立てには数週間〜数ヶ月かかることがあり、スムーズに進めるためには行政書士などの専門家による書類作成サポートが有効です。
Q3:家族信託って本当に必要?ちょっと大げさじゃないですか?
A:すべての人に必要ではありませんが、「柔軟な資産管理」が必要な方には非常に有効です。
たとえば、こんな方には向いています。
- 将来、不動産の売却が必要になる可能性がある
- 認知症後も、家族が自由に預金を使って生活費などを出していきたい
- 兄弟間で「財産の行き先」をしっかり決めておきたい(二次相続対策)
信託は仕組みがやや複雑なため、「まだ早い」と思う段階でこそ、相談しておくことが大切です。
Q4:兄弟で意見が合わないとき、どうしたらいいですか?
A:まずは、事実と制度を整理して「話し合える土台」を作りましょう。
相続や財産管理に関する争いの多くは、「情報が不透明なまま感情論になること」から始まります。
- 財産の全体像を共有できているか?
- 誰がどんな役割(介護・支援)を担ってきたか?
- 親の希望はどこまで反映されているか?
行政書士など第三者が間に入ることで、「家族の誰かの主張」ではなく「制度に基づいた説明」として話し合いがしやすくなります。
Q5:親が認知症になったあと、何から手をつければいいですか?
A:まずは「現状を整理し、何ができるか」を専門家と確認しましょう。
認知症の進行度、財産の種類、契約の有無、名義の状態……
これらを把握することで、次に取るべき行動が見えてきます。
【例】
- 遺言はもう作れない → 成年後見を検討
- 信託契約をしていれば → 発効手続きへ
- 家族の合意が取れそう → 相続対策の整理からスタート
焦るよりも、まずは「現状把握+優先順位づけ」が何より重要です。
Q6:どこに相談すればいいの?
A:行政書士は、相続・認知症対策の最初の相談窓口としておすすめです。
行政書士は、相続・遺言・後見・信託などに関する書類作成・制度設計に精通しています。
司法書士・税理士・弁護士などの専門家と連携することも可能なので、まずは全体像を整理する伴走役として活用してください。
まとめ:相続は「認知症になる前」が勝負。今こそ備えを
親が認知症になると、相続や財産管理に大きな制限がかかるという現実。
この記事でお伝えしてきたように、遺言も、生前贈与も、不動産の処分も、「本人の判断力」があってこそできることばかりです。
一度その力を失ってしまえば、できる手続きは限られ、自由度のない制度に頼らざるを得なくなります。
そうならないためにも、家族みんなが元気な今こそ、準備を始めるタイミングです。
今すぐ確認したい!備えのチェックリスト
以下の項目に、あなたはいくつチェックを入れられますか?
- 🔲 遺言書を作成している(または準備中)
- 🔲 親の財産(不動産・預金・負債など)をある程度把握している
- 🔲 名義や口座の状況を確認できている
- 🔲 認知症になった場合の制度(後見・信託など)を家族で話し合ったことがある
- 🔲 兄弟間で相続に関する意識共有ができている
- 🔲 専門家に一度でも相談したことがある
チェックが2つ以下の方
→ 今が“備えのスタート地点”です。焦らず一歩ずつ始めましょう。
チェックが3〜4つの方
→ 準備が進んでいます。抜け漏れを専門家と一緒に整理するとさらに安心です。
チェックが5つ以上の方
→ 素晴らしいです!あとは実行と継続的な確認だけです。
不安を感じた“今”が相談のベストタイミングです
認知症や相続に関する悩みは、「何から始めていいかわからない」というところで止まってしまうことが多いです。
ですが、正しい順序と知識があれば、誰でも無理なく備えを整えていくことができます。
当事務所では、以下のようなご相談に対応しています。
- 遺言書の作成サポート(自筆・公正証書どちらも対応)
- 成年後見・任意後見の制度説明と申立て書類作成
- 家族信託に関する設計支援
- 財産整理・名義調査・家族間の意識調整のご相談
- 他士業(司法書士・税理士・弁護士)との連携が必要なケースの橋渡し
まずは無料相談からお気軽にどうぞ!
大切なのは、行動のきっかけを逃さないことです。
あなたとあなたのご家族が、安心して将来を迎えられるよう、全力でサポートいたします。