目次
1. はじめに:なぜ「非上場株式の評価」が難しいのか?
「うちの会社の株って、いくらになるんだろう?」
これは、中小企業の経営者が相続や事業承継を考える際によく抱く疑問です。特に非上場企業の株式は、上場株のように市場価格が明確ではないため、「評価する」という作業が必要になります。
しかし、この「非上場株式の評価」は、実は多くの人にとって難解なテーマです。なぜなら、評価方法が複数あり、会社の規模や財務状況によっても異なり、税務上の取扱いにも注意が必要だからです。
さらに、相続やM&A、事業承継といったライフイベントが絡む場面では、金額の妥当性やトラブル回避の観点でも非常に重要な要素になります。
この記事では、非上場株式の評価がなぜ難しいのか?という素朴な疑問から出発しながら、相続やM&Aを控えた中小企業の経営者やそのご家族が知っておきたい基本的な考え方を、できるだけやさしく、実務的な目線で解説していきます。
また、「非上場株式の相続が気になる人は、なぜ遺言書を準備すべきなのか?」というポイントにも触れ、行政書士に依頼するメリットについてもお伝えしていきます。
2. 非上場株式の基本:評価ってどういうこと?
まずは「株式の評価とは何か?」という根本的な話から整理しておきましょう。
上場企業の株式であれば、証券取引所で売買されているため、株価(時価)が毎日表示されています。しかし、非上場企業の株式は市場で売買されていないため、明確な価格が存在しません。
それでも、相続・贈与・M&A・会社売却・事業承継などの場面では、株式の「価値(評価額)」を明らかにする必要があります。
なぜ評価が必要なのか?
以下のような目的で、非上場株式の評価が求められます。
- 相続税・贈与税の課税対象となるから
→ 税務署に提出する財産評価明細書に、適正な株価を記載する必要があります。 - 売却・譲渡時の価格の妥当性を示すため
→ 第三者や親族へ株式を譲渡するとき、双方が納得できる価格設定が求められます。 - 事業承継時の合意形成や遺産分割の参考として
→ 株の価値が明確でないと、他の財産とのバランスが取りづらく、争いの元になりかねません。
「会社によって価値が違う」のが非上場株の特徴
たとえ同じ資本金・従業員数の会社であっても、売上・利益・資産内容などの違いによって株式の評価額は大きく異なります。さらに、同じ会社でも評価時点の決算内容や業績動向によって価値は変動します。
ここが、上場株式と大きく違うポイントです。
たとえば以下のような要素が、評価に影響します。
- 純資産の多寡(資産-負債)
- 過去数年の利益や配当実績
- 同業他社との比較(業種別平均利益等)
- 会社の規模区分(大・中・小)
「評価額=実際の売買価格」とは限らない
ここで注意したいのが、「評価額」はあくまで理論上の価値だという点です。
実際に第三者に株を売却する場合は、事業の将来性や交渉によって大きく上下することがあります。
つまり、税務上の評価額と、市場的な売買価格は必ずしも一致しないということです。
この記事では、次章からこうした評価方法の種類や、ケース別の注意点について掘り下げていきます。
引き続き、「なるべく専門用語をやさしく」説明していきますので、ご安心ください!
上場株式と非上場株式の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 上場株式 | 非上場株式 |
| 売買の自由度 | 高い(市場で自由に売買可能) | 低い(取引制限があることが多い) |
| 価格の透明性 | 高い(市場価格がある) | 低い(客観的な価格が不明確) |
| 評価方法 | 市場価格を基準に評価 | 特定の算定方式で評価 |
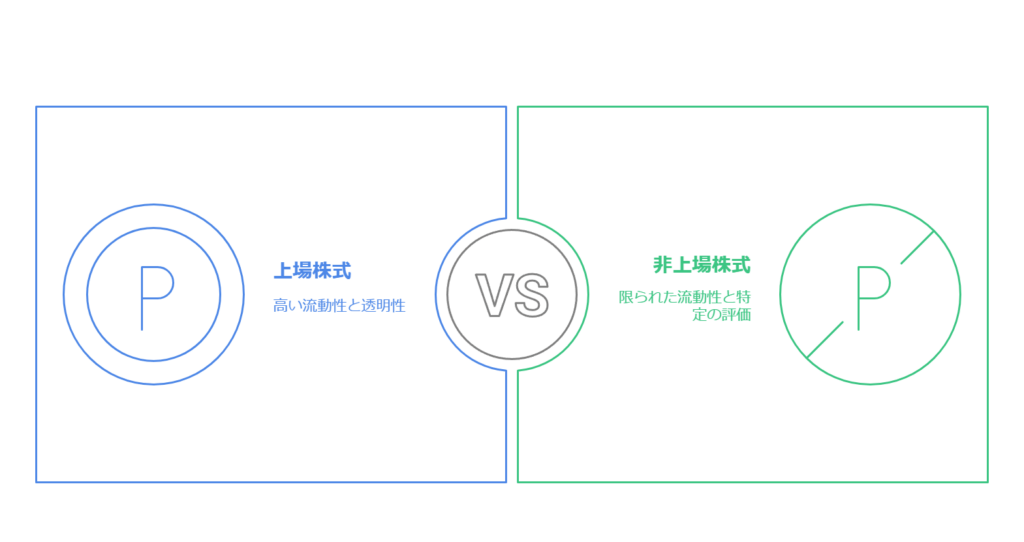
3. 評価の3つの方法(制度の一般論として紹介)
非上場株式の評価は、会社の規模や財務状況などによって、以下の3つの方法のいずれか、または複数を組み合わせて行われます。これらは、国税庁が発行している「財産評価基本通達」に基づいて、税務上の目的で広く用いられている方式です。
ここでは、それぞれの評価方法の基本的な仕組みと、どんな会社に向いているかを「ざっくり理解」できるようにご説明します。
① 類似業種比準方式(るいじぎょうしゅひじゅんほうしき)
✔ どんな方式?
非上場会社の業績を、上場している類似の業種の会社と比べて評価する方法です。
売上高や利益、配当などの実績をベースに、「この会社だったら、上場企業の何割くらいの価値があるか?」を計算します。
相続税・贈与税算定のベースとなる非上場株式の評価額を求める方式。評価対象と類似業種の上場企業株価の平均値に、課税年の類似業種1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額の3項目について各値を評価対象と比較した結果を掛け合わせて評価額を計算する。
✔ 向いている会社
- 規模が大きく、継続的に利益を出している会社
- 業績の推移が安定しており、比較可能な上場企業がある場合
✔ ポイント
業績が良ければ評価額は高く出やすく、逆に赤字や利益が少ないと低くなります。業種ごとの株価データ(国税庁の公表値)を使うので、タイミングや業界動向も影響します。
② 純資産価額方式(じゅんしさんかがくほうしき)
✔ どんな方式?
会社が持っている「資産 - 負債 = 純資産」の金額をベースに評価する方法です。言い換えれば、「会社を解散してすべてを清算したら、いくら残るか?」を基準にしています。
純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
✔ 向いている会社
- 小規模で利益実績が少ない会社
- 投資用不動産や現預金など、資産が大きい会社
- 休眠状態の会社
✔ ポイント
利益ではなく「資産ベース」で評価されるため、業績が悪くても資産価値が高ければ株価も高く出ます。評価対象となる資産の時価修正(帳簿価格と実勢価格の差)も重要です。
③ 配当還元方式(はいとうかんげんほうしき)
✔ どんな方式?
過去に支払われた配当を基に、株の価値を評価する方式です。将来の利益や資産ではなく、「この株を持っていたらどれだけリターンがあったか?」という視点で考えます。
配当還元方式とは、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10パーセント)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。
✔ 向いているケース
- 少数株主が評価対象となる場合
- 配当が安定して出ている会社
- 特定の制限がある持ち株(売却不可など)
✔ ポイント
この方式は評価額が低く出やすいため、相続税評価の一部場面で有利になることがあります。ただし、適用には一定の条件があるため、安易に使えるわけではありません。
どの方式を使うのかは「会社の規模」で決まる
これらの方式は、原則として会社の規模区分(大・中・小)によって適用方法が決まります。規模は主に以下の要素で判断されます。
- 年間売上高
- 総資産額
- 従業員数
また、複数の方式を組み合わせて平均を取る「併用方式」や、特殊事情がある場合の「特例評価」なども存在します。ですが、この記事ではあくまで一般的な制度の概要としてご紹介しています。詳細な適用判断は、税理士などの専門家に相談するのがベストです。
4. ケース別:非上場株式が問題になるシーン
非上場株式の評価は、会社のオーナーやその家族にとって「一生に一度あるかないか」の大きなテーマになります。そして、その重要性が表に出てくるのは、主に次の3つのケースです。
それぞれのシーンでどんな問題が起きやすく、なぜ「評価」が大切になるのかを、具体的に見ていきましょう。
ケース①:相続の場合
✔ どんな場面?
オーナー経営者が亡くなったとき、その方が持っていた非上場株式が相続財産として評価対象になります。
✔ 問題になりやすいポイント
- 相続税がどれくらいになるかが分からない
→ 非上場株の評価額によっては、思ったよりも高額な相続税が課されるケースも。 - 株式は分割しづらい
→ 土地や現金とは違い、株式は「共有」が難しいため、誰が引き継ぐかでもめる原因になります。 - 経営権と所有権が分離してしまう
→ 株を引き継いだ人が経営に関与できるとは限らない。逆に、経営している人が株を持たない状態になると、意思決定に支障が出ることも。
✔ なぜ評価が重要か?
相続税申告では、適正な評価額に基づいて株式を計上する必要があります。評価を誤ると、税務調査で指摘され、追加課税や延滞税が発生するリスクもあります。
ケース②:M&A(第三者承継)の場合
✔ どんな場面?
事業拡大、後継者不在、引退などの理由で、第三者に会社を売却するケースです。
✔ 問題になりやすいポイント
- 適正な株式の売却価格が分からない
→ 売る側と買う側で「会社の価値」の見方が異なると、価格交渉が難航します。 - 財務や業績の見せ方によって評価が変わる
→ 同じ数字でも、将来性やリスクの見せ方で印象が大きく変わります。 - 税金面の検討が漏れると手取りが減る
→ M&Aに伴う譲渡所得税や法人税の影響も見落とせません。
✔ なぜ評価が重要か?
企業価値の根拠を明確にし、買い手・売り手双方が納得できるようにするためです。
なお、本記事ではあくまで一般論として触れており、M&Aの実務には専門的な知識が必要です。
ケース③:事業承継(親族・役員への引継ぎ)の場合
✔ どんな場面?
後継者として、子や親族、あるいは古参役員に株式を譲渡・贈与する場面です。
✔ 問題になりやすいポイント
- 評価額によって贈与税・譲渡所得税が大きく変わる
- 株式の一部しか譲渡できない場合、経営権の確保が難しい
- 遺留分や他の相続人とのバランスも考慮が必要
✔ なぜ評価が重要か?
後継者が株式をどう取得するか(贈与・売買・相続など)によって、税務上の取り扱いや手続きが異なります。また、遺言や持ち分比率の調整にも直結するため、早い段階での評価と対策が極めて重要です。
まとめ:評価は「将来のトラブル防止策」
これらのケースに共通して言えるのは、「非上場株式の評価をあいまいにしておくと、後々トラブルになる」ということです。
- 課税額が読めない
- 財産分割がうまくいかない
- 納得感のある価格提示ができない
こうした事態を防ぐには、早めの評価と、専門家との連携がカギになります。
次章では、特に「相続」においてなぜ遺言が重要なのか、そして行政書士がどのように支援できるのかを見ていきましょう。
5. 非上場株式の相続が気になる人へ:なぜ今、遺言が大切なのか?
非上場株式を持つ中小企業オーナーにとって、相続対策の要(かなめ)となるのが「遺言書の作成」です。
「遺言なんて、うちは家族仲がいいから必要ないよ」と思っている方も多いですが、実は家族仲の良し悪しにかかわらず、株式のような分けづらい財産がある場合は、遺言がないことで深刻なトラブルに発展することがあります。
なぜ「非上場株式」に限って遺言が重要なのか?
✔ 分けづらい
株式は、土地や預貯金のようにきれいに分けることができません。
しかも、議決権が付いているため、「誰がどのくらい株を持つか」で経営権や発言力が大きく変わります。
✔ 揉めやすい
株式を持っていない相続人が「自分には不公平だ」と感じることで、相続トラブル(争族)が発生することがよくあります。
結果として、経営が一時的にストップしたり、事業承継に失敗したりするリスクが高まります。
✔ 法定相続だけでは対応しきれない
民法に従えば、配偶者や子どもに均等に分けることになりますが、それでは経営の一貫性が失われることがあります。
だからこそ、誰に何を残すかを明確に指定できる「遺言書」が極めて重要なのです。
遺言があるだけで、相続手続きは劇的にスムーズになる
遺言がある場合とない場合では、手続きの煩雑さに大きな差があります。
| 項目 | 遺言がある場合 | 遺言がない場合 |
|---|---|---|
| 株式の名義変更 | 遺言内容に従って1人で手続き可能 | 相続人全員の合意が必要(時間と手間がかかる) |
| 相続税申告 | 計画的に評価・準備できる | 手続き中に期限が迫ると混乱しやすい |
| 経営の継続 | 指名された後継者がすぐに動ける | 経営判断が停滞し、事業に悪影響が出ることも |
行政書士に依頼するメリットとは?
「遺言書=弁護士に頼むもの」と思われがちですが、遺言作成は行政書士が得意とする分野です。特に中小企業の経営者にとって、行政書士を活用することは大きなメリットがあります。
✔ メリット①:法的に有効な遺言が作れる
行政書士は、遺言書の形式・文言・内容が民法に適合しているかを確認しながら、正式な遺言書を作成します。自筆証書遺言、または公正証書遺言の作成支援にも対応できます。
✔ メリット②:税務・登記の専門家と連携してくれる
行政書士は、税理士・司法書士・弁護士と連携して、相続全体をチームで支援する体制を整えているケースが多く、ワンストップで相談できます。
✔ メリット③:家族の将来を見据えた提案ができる
「とりあえず作る」ではなく、「誰に何をどのように残すか?」という視点で、争いにならない遺言書の作成をサポートしてくれます。
行政書士への相談は「早ければ早いほど良い」
経営者の年齢や健康状態が問題になる前に、遺言書の準備を進めることが、会社と家族を守ることにつながります。
特に非上場株式は、遺言の有無によって「経営の未来」が大きく変わる資産です。
まだ何も準備していないという方は、ぜひ行政書士への相談を第一歩として検討してみてください。
6. 非上場株式評価に関するよくある誤解と注意点
非上場株式の評価について、専門家以外の方が抱きやすい誤解は少なくありません。特に、相続や事業承継の場面では「勘違い」や「思い込み」が、のちのち大きなトラブルにつながることもあります。
ここでは、よくある誤解や見落としやすいポイントを、いくつかご紹介します。
誤解①:「決算書を見れば株価なんてすぐに分かる」
確かに、評価のベースになるのは決算書です。しかし、評価では「帳簿上の数値」をそのまま使うのではなく、現実的な価値(=時価)に修正する必要があります。
- 土地や建物は「固定資産台帳の価格」ではなく「時価」に修正
- 不良債権や遊休資産は減額評価
- 資産の含み益・含み損も考慮 など
つまり、決算書はあくまで出発点であって、そこから大きな調整が必要なのです。
誤解②:「会社が赤字だから株の価値はゼロでしょ?」
赤字だからといって、株式の評価がゼロになるとは限りません。
たとえば以下のようなケースでは、赤字企業でも一定の評価額がつくことがあります。
- 資産(土地・現金など)を多く保有している
- 一時的な赤字であり、将来の収益性が高い
- グループ会社との取引があるなど、営業基盤が強固
特に純資産価額方式では、利益ではなく資産の内容が評価の主軸になります。
誤解③:「相続が起きてから評価すれば間に合う」
これは大きな落とし穴です。
相続発生後の手続きは、限られた時間の中で非常に多くの作業が発生します。
非上場株式の評価は時間も手間もかかるため、事前に準備していないと、納税期限(通常は相続開始から10か月)に間に合わないことも。
評価に時間がかかると、
- 相続税申告に遅れが出る
- 申告が雑になり、税務調査のリスクが高まる
- 相続人同士で混乱が起きやすい
などの問題が生じます。
特に非上場株は専門性が高いため、「評価の準備は早め早め」が鉄則です。
誤解④:「税務署と揉めるのは一部の資産家だけ」
非上場株式の評価は「主観」が入りやすいため、税務署との見解がズレやすい資産です。
中小企業オーナーであっても、以下のような場合には税務署から指摘を受けることがあります。
- 評価方法の選択を誤っている
- 修正すべき資産をそのままにしている
- グループ会社との関係や利益の偏在がある
- 配当の履歴が評価と矛盾している
こうしたリスクを避けるためにも、評価には一定の専門性と経験が必要です。
評価は「税額」を決める以上に、「人間関係」を守るためのもの
非上場株式の評価は、単なる金額の問題ではありません。
- 相続で兄弟姉妹の不信感が生まれる
- 後継者が他の相続人から非難される
- 会社経営に影響が出る
こうした人間関係のトラブルを防ぐためにも、「納得感のある評価」がとても重要です。
そしてそのためには、評価方法を正しく理解し、適切な支援を受けることが欠かせません。
7. よくある質問Q&A
非上場株式の評価や相続に関する情報は、専門的で分かりにくいものが多いですよね。
ここでは、中小企業のオーナーやご家族からよく寄せられる疑問に、できるだけわかりやすくお答えしていきます。
Q1. 非上場株式の評価は、毎年やるべきですか?
A:必ずしも毎年必要というわけではありません。
ただし、相続や事業承継、M&Aなどの予定がある場合は、定期的に評価しておくことを強くおすすめします。
会社の業績や資産構成によって評価額は大きく変わるため、「今の株価の目安」を把握しておくことで、対策や準備がスムーズに行えます。
Q2. 自分で評価することはできますか?
A:制度上は可能ですが、実務的にはおすすめしません。
評価には、税務知識や財務分析、時価評価の判断など専門的な知識が必要です。
誤った評価を行うと、税務調査で否認されたり、相続人間でのトラブルに発展する可能性もあります。
評価が必要なときは、税理士などの専門家に依頼するのが一般的です。
Q3. 生前に株式を贈与すれば、相続対策になりますか?
A:有効な場合もありますが、一概には言えません。
生前贈与を活用することで、相続時の財産を圧縮できるケースはあります。
ただし、
- 贈与税の対象になる
- 贈与後も持ち株比率によって経営権が変わる
- 時価評価が必要になる
など、慎重な設計と評価が必要です。
贈与と相続、どちらが良いかはケースバイケースなので、専門家のアドバイスを受けて判断しましょう。
Q4. 行政書士と税理士、どちらに相談すればよいですか?
A:それぞれ役割が異なるため、目的に応じて相談先を選ぶのがベストです。
| 相談内容 | 適した専門家 |
|---|---|
| 遺言書の作成、相続の全体設計 | 行政書士 |
| 非上場株の評価、税務申告 | 税理士 |
| 相続登記や不動産の名義変更 | 司法書士 |
特に遺言や事業承継の初期相談では、行政書士が窓口となって、必要に応じて他士業と連携してくれるケースも多くあります。
Q5. 非上場株式の評価額が「ゼロ」になることはありますか?
A:理論上は可能ですが、実務上はあまりありません。
例えば、赤字続きで純資産がマイナスだったり、事業停止中で事実上無価値と判断される場合など、一定の要件が揃えば「評価額が非常に低い」ことはあります。
ただし、会社に現金や不動産などの資産がある限り、ゼロ評価は難しいと考えておいた方がよいでしょう。
Q6. 株式を分けたくないのですが、法的に大丈夫ですか?
A:遺言書で「誰にすべてを相続させるか」を明記することが可能です。
ただし、他の相続人には「遺留分」という最低限の取り分を請求する権利があります。
株式の集中保有を目指す場合は、他の財産でバランスをとる工夫が必要です。
このような設計は、行政書士が得意とする分野ですので、ぜひ早めに相談してみましょう。
Q7. 株式の評価をしておけば、それで安心ですか?
A:いいえ、評価はあくまでスタートラインです。
評価は重要な要素ですが、それだけで相続や事業承継の問題が解決するわけではありません。
評価に基づいて「どう分けるか」「どう引き継ぐか」まで考えることが重要です。
そのために必要なのが、遺言書の作成や家族との合意形成、後継者の明確化です。
早い段階からの準備が、将来のトラブル回避につながります。
8. まとめ:今できる一歩を踏み出すために
非上場株式の評価というテーマは、たしかに難しく感じられるかもしれません。
しかし、本記事を通じてお伝えしたかったのは、「難しさ」よりも「早めの行動」の大切さです。
本記事のポイントをおさらい
- 非上場株式の評価は、相続・M&A・事業承継などで不可避なテーマ
- 評価方法には「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「配当還元方式」があり、会社の規模や状況で異なる
- 評価は税額だけでなく、家族関係や経営の安定にも影響する重要事項
- 特に相続時には、株式の取り扱いを巡ってトラブルになるリスクが高い
- そのリスクを減らすために、遺言書の準備は極めて重要
- 遺言作成は行政書士に依頼することで、法的にも実務的にも安心できる
行動するなら「今」が最善のタイミング
「まだ先のことだし…」
「元気なうちは考えなくていいかな…」
そう思っている方こそ、今がチャンスです。
なぜなら、元気で判断力のあるうちにしか、できないことがたくさんあるから。
- 「今の会社の株って、いくらぐらいなのか?」
- 「誰に何をどれくらい残したいのか?」
- 「自分がいなくなったあと、会社と家族はどうなるのか?」
こうした問いに対して、答えを整理しておくことは、経営者としての最後の責任とも言えるかもしれません。
行政書士への相談から、第一歩を踏み出しましょう
- 「評価はまだだけど、何から始めたらいいかわからない」
- 「遺言を書いた方がいいとは思うけど、不安がある」
- 「誰に相談したらいいのか分からない」
そんな方にこそ、行政書士への初回相談をおすすめします。
税務申告や不動産登記など、必要に応じて他の専門家と連携しながら、相続・事業承継を一貫して支援できる体制が整っているケースが多くあります。
最後に──「評価すること」は、自分と家族を守ること
非上場株式は、企業のオーナーにとってただの資産ではなく、「会社の未来」と「家族の安心」の両方に直結するものです。
だからこそ、その評価や取り扱いを後回しにせず、少しずつでも、今日から準備を始めてみてください。
評価の正しい理解と、遺言による備えが、あなたとあなたの家族を守る最初の一歩になります。




